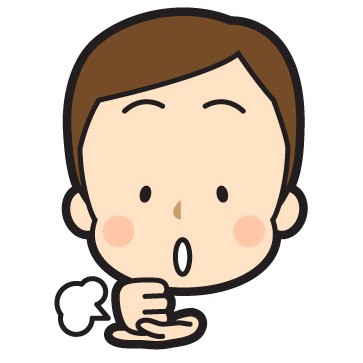気密ってご存じでしょうか。
気密は断熱と切っても切れない仲なんです。
今回は高気密住宅の重要性についてお話しします。
気密とは
簡単に言うと、「隙間のなさ」です。
高気密な住宅とは、「できるだけ隙間をなくし、外と室内の空気の出入りを少なくしている住宅」と言うことになります。
隙間が少ないと、部屋の中の空気が悪くならない?
そうではありません。
むしろ、隙間がある方がデメリットが大きいのです。
気密性が低いと生じる4つの問題?
①冷暖房の利きが悪い
気密性が低い=家に隙間があると言うことです。
隙間があると、そこから空気も自由に出入りできます。
外の空気がどんどん入ってきます。
せっかく断熱にこだわった家を作っても、気密性能が低いと、夏は暑く冬は寒い家になってしまいます。
②結露が発生するリスク

断熱性能が低いと、結露リスクがあるって言う話だったよね。
気密性能が低い家でも、結露のリスクが存在します。
結露とは
暖かい空気が冷やされると水蒸気が水に変わり、水滴が生じる現象です。
結露が発生すると、木材が腐食しやすくなります。
木材自体がもろくなるだけでなく、カビやシロアリ発生の原因になります。
できるだけ結露しない家を作る必要があります。
気密性能と結露の関係
家に隙間があると、隙間から空気が漏れます。
例えば冬期では、部屋の暖かい空気が壁の内部に入り込みます。
壁の内部は部屋の中より冷えていますので、壁の中で結露します。
壁の中の結露のことを壁内結露とも言うよ
窓の周囲の結露は、拭き取ればよいのですが、壁内結露の場合はそうはいきません。
濡れたままだと、木材が腐りやすくなり、シロアリ被害の原因にもつながります。
壁内には構造上重要な木材も多く、それが腐ったり、シロアリに食べられたりすれば、耐震強度が下がる恐れがあります。
柱や耐震ボードが気づかないうちに!?
③雨漏りの原因にもなり得る

水は空気よりも粒子が大きいため、空気は通る隙間=雨漏りではありません。
しかし、隙間の大きさによっては、当然水も入り込みます。
雨漏りの原因になったり、壁内に水が染み込んだりすることで結露同様、木材が腐る可能性があります。
④換気ができなくなる

気密性が低いと、隙間から空気の出入りがあります。
換気になっていいんじゃないの?
意図しない隙間による空気の出入りが問題になります。
換気システムの義務化
平成15年から住宅における換気システムが義務化されました。
隙間風の多い古来の住宅と比べると、近年の住宅は対策をしていない家でさえ、機密性が増しています。CO2濃度が高まったり、ハウスダストがたまったりすることで、健康被害が発生するようになりました。その対策として、2時間で部屋の空気を全て入れ換えることのできる換気システムの導入が義務化されました。
隙間が多いと?
換気システムが機能しない可能性があります。
部屋の遠くの空気を排出したいのに、意図せず隙間から空気が入ってくることで、計画通りに換気ができない可能性があります。
穴がいっぱい開いたストローで、水を飲むようなものか
現在の家づくりにおいては、換気システムを計画通りに稼働させるために、機密性が求められています。
気密性能はC値!
C値とは、家の大きさに対して、どのくらいの隙間があるのかを表す数値です。
C値=家全体の隙間の合計(㎠)÷建物の延べ床面積(㎡)
で表されます。
C値が小さければ小さいほど、気密性能が高い家と言うことになります。
C値は何が影響する?
鉄骨造よりも木造
一般的に、木造の方が鉄骨造よりも、C値が上がりやすいと言われています。
鉄骨造は、地震の揺れを逃がすため、隙間を空けて建築する必要があります。
冬期と夏期で伸縮するので、それも考慮する必要があります。
ドアや窓の仕様
両側からスライドさせることのできる引き違い窓、和風の家で見られる引き戸は気密が取りにくいと言われています。
職人さんの施工品質が何より大切!
家の隙間は、隙間ができやすい箇所をあらかじめ把握し、細部まで隙間を埋める気密処理が欠かせません。
開口部、コンセント、配管、建材の接合部など、無数にある小さな隙間を一つずつテープや発泡ウレタンで埋めていきます。
現場の職人さんの意識と技術力があって初めて高気密な住宅ができます。
逆に言えば、丁寧な施工をしている会社は、自然と高気密な住宅に近づきます。
私は営業さんにこんなことを言われたことがあります。
最近C値にこだわられる方も多いですが、
そこまで変わりませんよ。
こういった場合は要注意です。
気密に自信がある発言なのか、
気密を重視していない会社なのか分からないね。
気密測定の必要性
そこで、気密測定をしているかどうか、が一つの基準となります。
C値は同じ作りの家でも1邸1邸異なります。
建てた家に隙間がどのくらいあるかは、実際に建ててみないとわかりません。
C値は、家が建ったタイミングで計測器具を持ち込んで測定を行います。
UA値や断熱等級は設計の段階で決まりますが、C値は家を建てたタイミングで決まります。
高気密住宅!
平均C値○○!
を謳う住宅メーカーも多くあります。
しかし、C値は職人の施工品質によります。
カタログやモデルハウスのC値が優秀であっても、私たちの家が必ずその値になるという保証はありません。
気密性を大切にする場合、
- 「C値○○以下を保証」と言うメーカーを選ぶ
- 営業さんに気密測定をしてもらう
ことをオススメします。
気密測定は安心だけではない
気密測定をして、思うような結果が出なければ、気密処理を再度依頼することが可能です。
また、気密測定が行われる現場では、施工精度が求められます。
職人さんもより丁寧な施工を心がけてくれる可能性が高まります。
気密測定する現場では、いい意味で緊張感を持って仕事に臨むことができるそうです。
どのくらいのC値がよいの?
C値0.7~0.5以下を目指す
一般的にC値1.0以上の住宅は高気密住宅と言われます。
それよりも下回るC値0.7~0.5以下を目指したいと思います。
どうして?
C値は低ければ低いほど良いとされています。
しかし、求めすぎるとコストがどうしてもかかってきます。
また、どうしても隙間は存在するため、C値0.0は絶対と言っていいほど不可能です。
C値が0.7~0.5以下であれば、気密性能もそれなりに担保できます。
気密住宅になれている会社であれば、気密テープや発泡ウレタンの追加処理の費用をそこまでかけずに達成できる水準となります。
1.0だめなの?
気密性能は経年劣化します。
木は伸縮を繰り返しますし、地震等の揺れもあります。
隙間はどうしても少しずつ大きくなります。
引き渡し時はC値1.0だったとしても、年月が建てれば1.2、1.5と低下していく可能性があります。
経年変化後にC値1.0程度を目指すためにも、C値0.7~0.5を目指したいと思います。
まとめ
- 快適な家を目指すなら、断熱だけでなく気密性能も
- C値を知るためには建てた家で気密測定を
- 気密測定は施工不良を防ぐ
- C値は求めすぎず、0.7~0.5程度を目指す
気密についてお話ししました。
全棟C値を測定しているメーカーは多くありません。
まずは営業さんに気密測定したいことを伝えてみて、希望の数値をお願いするのが良いかと思います。
住宅の構造や建材の仕様にもよりますので、数字にこだわりすぎるときりがありません。
職人さんにできるだけ丁寧な施工をしていただくための気密測定と心得て、お願いしてみてはいかがでしょうか。